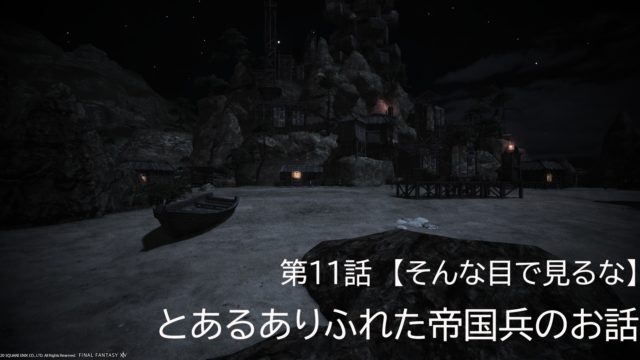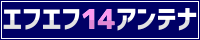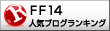父がいなくなり、家から灯が消えるように家族は落ち込んだ
正確に何があったのかは結局わからない、何を聞いたところで父がいないことに変わりはない
そんな中でも母は必死に働いた
苦しくとも、家族を放棄しなかった
「父さんは運がなかったんだ、けれどその分お前はきっと運がある」
「父さんの運はお前をきっと守ってくれる」
「母さんがお前が大きくなるまで絶対に育ててみせるから、お前は幸せになりなさい」
まるで父の仇を討つように、はたまた理不尽から家族を守るように
他の家族が、子どもが、子どもたちが櫛の歯が抜けるようにポロポロとボロボロになっていくなか、母は必死になって働き、育て、養った
決して裕福ではなかったけれど、不自由を感じずに大きくなった
空腹の経験が少ない分、少しだけ人にも優しくなれた
幼さ特有の偏見や穿った思考はあったけれど、それでもそれなりに普通の生活と成長をしていた
属州であるが故の差別や理不尽は感じていたけれど、それでも持ち前のシンプルな性格と母の教育が歪むことを許さなかったのだろう
しかし、運は理不尽だった
父がいなくなって10年、少しずつ平和と明るさが戻ってきた家族
母の尽力で帝国の用意したものではあったが教育も受けられた
それを当たり前に享受し、それなりに真面目に不真面目に勉強し、日々を過ごした
そんな日常はある日、混乱と喧騒にすりつぶされた
どこで何が起こっているかは知らないが、大きな軍勢が小さなこの町を行軍した
それは、たまたまその進路にこの町があっただけなんだ
普段がどうかはわからないけれど、軍勢は焦っているように思えた
無口に足早に、目つきだけ鋭く
そんな時は何もせずに家にいれば通り過ぎる
家にいれば、邪魔にならないようにおとなしくしていればよかっただけなのに
その日、母は嬉しかった
その日は卒業式、出来の悪い愛息子が頑張った証の日
晴れの日を見届けようかと思ったけれど、生意気にも「恥ずかしいから来ないでくれ」と言ってきた
そういう年齢になったこともまた嬉しいが、ただ家で帰りを待つのも面白くない
今日この日を目いっぱい祝ってやろう、運が向いてきたと誉めてやろう
食べきれないほどのごちそうを作って、今日という日を忘れられなくしてやろう
そんな気持ちが、危機感を鈍らせた
混雑する大通り、見物に来た町民と行進する軍勢
そんなものを見ている場合じゃないと店に回り、ごちそうの材料を揃える
張り詰めた空気の軍人の前に、急ぐ母はほんの一歩ほど近づいてしまう
息子を喜ばせる為の食材が行進中の軍人に当たる
謝るべきだった、地に頭を擦り付けて許しを請えば問題はなかったかもしれない
はやる気持ちを抑えられない母はそんなことを思いつきもしなかった
「なにすんだい!」
その言葉にしまった!という表情をする母と、武器を振り下ろす軍人の行動は同時だった
成長を祝うはずだったごちそうの欠片たちは地面にちらばり、雑踏に踏みつぶされていった……
朝、笑顔で送り出してくれた母は、その夜変わり果てた姿になった
家にはなんの明かりもなく、朝に干された洗濯物が嘘くさくて
母の存在は家のどこを見ても感じ取れるのに、肝心の母がいない
母は物体に成り果て、何も語ってはくれない
泣いた、自分でも信じられないくらい大きな声が出た
夜空に噛みつかんばかりの大声で泣いた
母の死を悼む人が訪ねてきても、母を殺したものを憎み咎めることを口にするものはいない
母を殺したことを詫びる者はいない
母は病気で死んだわけでも自死したわけでもない、大衆の前で明らかに殺害されたのに
母は属州の一般人で、相手は帝国の軍人
母の死は帝国軍にとって自分にまとわりついた虫を振り払った程度の事でしかない
町の人にとって母は荒れ狂った災害の犠牲者に他ならない
これが、強さなんだ
理不尽で、強大で、膨大な強さだ
帝国を憎む気持ちはない
運が悪いから属州に生まれ、父も母も死んだ
運とは強さだ
理不尽をねじ伏せるもっと大きな理不尽だ
帝国とは、強大な理不尽なんだ
帝国の軍人になれば
偉くなれば
父や母が求めていた幸せが手に入る
強大な運が掴める
いや、運すらも理不尽な力でひれ伏せさせることができる
もう一度心の中で繰り返す
帝国を憎む気持ちはない……ないんだ!
強くなるんだ、運をつかむんだ
そうだ
出世しよう そうしよう
喉も擦り切れ流す涙も枯れ果て疲れきって母の傍らで眠りにつくとき、朧気にそう思った
母は何も言わず、冷たいままだった
子どもであることはその日、本当の意味で終わった
母の死からしばらくの間、できる仕事はなんでもやった
悪事こそ手を出さなかったが、生きる為ならゴミも漁った、体躯を生かした荒事もこなした
その日を生き抜くことだけに集中した
明確に理由がわかるわけではなかったけれど、確信できることがあった
もうすぐ帝国は軍関係の増員を行うということ
母を殺した一団の行軍、それは大きな軍事行動があったということ
戦争があれば、軍人は死ぬ
死ねば人を補充しなければいけない、その欠員が多ければ属州からだって募集をしなければならないはず
運が味方をするなら、そうなるはずだ
その時が来るまで、なんとしても自分を強く大きく維持して生きていかなければいけない
その時が来た時に体を壊していては意味がないのだ
生きて、生きて、生き抜いてその時を待つ
そんな気持ちを祝福するように、ある日空が燃えた
遠く彼方、カルテノーが赤く紅く焼け輝いた
それを見た町の人が混乱し逃げ惑う中、その遠くに輝く奔流に視線を向け、一人大声で笑っていた
渦巻く風と光の中、笑い続けた
運は今、きっと味方についている―――